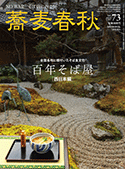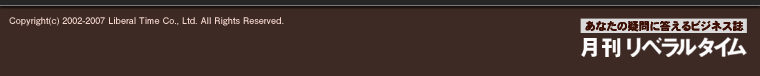最新ニュースへ戻る
 金融機関で貸金庫を巡る事件が相次ぐ |
「隠し資産」の隠れみのだった
「貸金庫」 2025年3月24日 銀行の貸金庫を巡る窃盗事件は、三菱UFJ銀行(2024年11月公表)に続いてみずほ銀行(公表は25年2月だが発覚は19年)、ハナ信用組合(25年3月公表)で次々と明らかになり、同種事件が多くの金融機関に広がっている実態がうかがえる。銀行関係者の間では「パンドラの箱が開いた」といわれており、貸金庫をめぐる「闇」の深さが浮かび上がった形だ。貸金庫は銀行法上、付随業務として設置を認めてられているもので「有価証券、貴金属その他の物品の保管」とされている。現金がないのは預金になってしまうからで「現金が中に入っているのは想定外」というのが建前だ。しかし、国税OB税理士は「税務調査では何度も貸金庫から現金を発見した」と明かす。実際、国家公安委員会が毎年公表している「犯罪収益移転危険度調査書」にも貸金庫が犯罪に使用されたことが記されており、検察幹部も「家宅捜索で貸金庫に入ることは少なくない。捜査の過程で発覚したため公表されなかっただけで、貸金庫が犯罪の温床になっていることは常識」といい切る。一方、現金を入れている側も、一つの貸金庫の現金が発覚すると隠し資産全体が明るみに出るため、トラブルは穏便に収まるのが普通だという。ある銀行関係者は「顧客が貸金庫の確認を申し出て、現金が足りなかったケースでは『忘れ物がありました』と収めると聞いた」という。窃盗が前提とも受け取れる発言だ。加藤勝信金融相は一連の不祥事を受けて「(貸金庫の)あり方そのものを検討していく必要がある」との認識を示す。金融庁は近く、銀行等へ向けた「監督指針」を改正し、貸金庫管理の厳格化を求めるが、問題はそのようなレベルではなさそうだ。 |
好評発売中!

東京近郊 極上蕎麦 2025年
【路線別】「手打ち」&
「立ち食い」名店勢揃い!
Amazonでも購入可能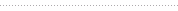
好評発売中!

「日本財団」理事長の活動記録
世道人心に質す!
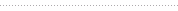
全ての単行本を見る

東京近郊 極上蕎麦 2025年
【路線別】「手打ち」&
「立ち食い」名店勢揃い!
Amazonでも購入可能
好評発売中!

「日本財団」理事長の活動記録
世道人心に質す!
全ての単行本を見る